和食の基本調理器具
調理道具は非常に種類が多いもの。
店に買いに行きますと、あまりに厖大かつ多種類の道具に思わず目移りしてしまい、不必要で役に立たない物を購入したり、結局何も買わなかったという事もあるでしょう。
「何に使うか」を明確にしておくのがポイントでしょうね。
これは和食調理に必要な道具だろうな。
そう思える道具を絞り込んで紹介致します。
まな板
色々なまな板がありますが、庖丁の刃を感じれる木製、なかでもやはりヒノキがおすすめのまな板です。ヒノキは防虫効果もあり、適度な硬さもまな板に向いていて使いやすいですよ。
まな板の使用法と手入れの仕方
使用前に水で濡らしましょう。
濡れ布巾をかけておくとさらにニオイが移り難くなります。
使用後はクレンザーとタワシを使って洗い、風通しのよい場所に立てて乾燥させます。時々ハイターで消毒するといいでしょう。
魚などを捌いて強い臭いがついたら、塩を振ってタワシでみがき、酢をかけて洗い、最後に熱湯をかけて消毒し、水洗いして乾かしておきます。
カビがはえてしまったら、布巾をかけて斜めに置き、上からハイターをかけてしばらく放置しておきましょう。その後水洗いします。
基本の和食包丁
庖丁の種類はかなり多いです。
和食の道具→包丁
細かく言い出せばきりがありません。
家庭調理に優先順位が高いものから紹介していきます。
牛刀
牛刀は、炭素鋼かステンレスを「型抜き」して油焼きにした洋庖丁の一つです。サビに強く、表・裏に刃が付いている両刃包丁になります。中子が柄の先まで入ってるので頑丈で、粗い使用にも耐えます。
(※冷凍品は冷凍庖丁、骨切りは出刃を使う事)
牛刀はあらゆる調理に万能に使えますので、「最初の1本」はこれがよいと思います。少し大きめの牛刀を選びますと「大は小をかねる」で万能性がさらに高まります。(ただし無理して大きなものを買うと逆に使い物にならないので注意。刃渡り210~300mmくらいが丁度良く、それ以上はかなり調理慣れしないと扱いきれません。自分に合うサイズを選びましょう)

※長さは刃の長さを表しています
※庖丁は刃物ですから信頼性が大事です
「安くて良いもの」を期待しない方が賢明。
あまりにも安い品はなんらかの問題があります。
あるていどしっかりした物を選ばないと後悔します。
三徳庖丁
三徳包丁は鎌型をしており、牛刀と菜切りを併せ持っている万能型和庖丁です。肉・魚・野菜と、やはり「1本あれば足りる」庖丁。

145mm~165mmが使い良いです。
180mmは少し上級者向けかも知れません。
牛刀か三徳、好きなものを1本目の庖丁とし、2本目はペティナイフにするといいでしょう。
ペティナイフ
120mm前後の小さな牛刀です。
ペティナイフと呼び、よく使う庖丁です。
野菜・果物の皮むきやカット、小さな材料、細かい作業に便利。


Tojiro-PRO ニッケルダマスカス鋼割込 ペティナイフ105mm

出刃庖丁
魚や鶏をさばく庖丁です。
和庖丁は、非常に硬い鋼(はがね)と軟鉄を貼り合せて造った片刃庖丁で、鋭い切れ味が特徴です。
※下に紹介するのはステンレス製で、貼り合せとは少し異なります
中でも出刃は厚みがありますので、固い魚の骨や殻付きのエビやカニなど魚介をさばきやすい構造になっています。
大きな鯛などをさばく出刃、アジなど小魚をさばく小出刃があれば便利です。1本なら7寸(210mm)くらいの出刃が使い良いでしょう。

サビに強いモリブデンバナジウムステンレス刃
持ちやすいハンドル
GLOBAL 小出刃 刃渡り12cm

柳刃庖丁
刺身庖丁は第一に切れ味。
なので、錆はしますが、和庖丁本来の「鋼付け」がおすすめ。
あまりに短い刺身庖丁は意味がありません。
できるだけ八寸(240mm)以上のものを選んで下さい。

薄刃庖丁
普通ならここで「菜切り庖丁」とくるところですが、菜切りは野菜を切る庖丁です。それならば一段上の薄刃庖丁を選んだ方がよいです。
同じ用途に使えますし、切れ味は遥かに優れています。
その薄い刃と鋭い切れで「かつらむき」の習得にも使えます。
刃先が使える鎌型(関西型)が便利です。


庖丁の手入れ
使った庖丁はそのつど水洗いし、使い終えたら洗剤で柄の周囲までよく洗い、水気を完全にふき取って仕舞いましょう。
庖丁研ぎは「簡易研ぎ器」を使わず、必ず砥石を使いましょう。
→庖丁の研ぎ方
使う前に砥石を30分ほど水につけておくこと。よく使う人は濡れた布巾で砥石を巻きつけてビニール袋に入れておいてもいいでしょう。
高級で高価な砥石を使う必要はありません。
下のような千番くらいの丈夫な石が適当です。
#1000 中仕上用 Amazon
関連記事:使いやすい万能包丁
和食用の鍋類
鍋の性能は熱伝導率で決まり、銅製の鍋がずば抜けています。
しかし高価で、扱いも面倒で手間がかかり、家庭向きとは言えません。
ステンレスの弱点である熱伝導率の悪さもなく、安くて手入れも簡単、味噌汁や煮物や茹でものに手軽に使える。それがアルミ製の「ゆきひら鍋」です。さらに打ち出しをしてある「槌目」は、熱の当たる部分が大きくなり、火がまわりやすくなっています。

※アルミの弱点は酸に弱いこと。
鍋に料理を入れっぱなしにしないで下さい。
★落とし蓋
行平鍋のフタにしたり、煮物の他豆腐などの水切り時や出し巻き玉子の取り出し時など和食作りには欠かせないアイテム

浅鍋
和食の煮物で重宝するのが浅鍋。
材料を一段にして煮る煮っころがしや煮しめ、魚の煮付けなどに。


本製品はカレイの煮付けや里芋の煮っ転がしなどの和食、ホワイトソースなどのソース作りにピッタリの浅型両手鍋。直径25㎝の大型なので、魚を丸ごと一匹調理することも可能。熱がムラなく伝わるので素材への火の通りも均一に。
ジオ 浅型両手鍋商品説明
また、蓋と本体が密着する構造により、蒸気を内部を密閉状態に保つ「ウォーターシール効果」が起こるため、定温・定圧に近い状態で調理できる。この調理法なら熱によるビタミンやミネラルの破壊を最小限にとどめ、素材の旨味を損なうこともない。縁や鍋底に段差がなくお手入れしやすいので日常使いに最適
両手深鍋
出汁とり、めんゆで、スープ、シチュー、煮込み系の料理に。

ホーローミルクパン
ミルクを温めるだけのものではありません。
ほうろうは優れた素材です。
ポン酢、合わせ酢作り、ジャムやホワイトソースに。
酸に強いので酢を使う料理はこれで。
離乳食作りにも最適。
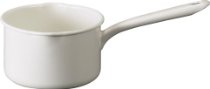
蒸し器
蒸し物はやはり「せいろ」が一番美味しく仕上がります。

和食ならではの、流し缶が入る角型の蒸し器も欲しいところです。
茶碗蒸しもこれが良いですね。
フライパン
フライパンは「鍋」の一種であり、炒めるだけの用途に限定されません。
和食でも丼物などで非常に重宝します。考え方ひとつであらゆる使い方ができますよ。
さまざまな材質があるが、使い込むほどに油が馴染む鉄製に勝るフライパンはないです。

万能に使える中華鍋、「せいろ」とサイズを合せましょう。片手鍋が使いやすいです。

中華鍋の万能さはジャーレンとセットで使ってこそです。ジャーレンがあると炒め物や揚げ物が驚くほど速く完成します。

※鉄のフライパンは防錆加工をしてあります。
購入したらカラ焼きをしてこれを焼いてしまい、1度よく洗剤で洗います。その後でクズ野菜などを油で炒めたり、古い油を入れて加熱したりして油を充分に馴染ませます。その後は洗剤で洗わないようにしましょう。金属ではないタワシでさっと水洗いし、から焼きして乾燥させます。
卵焼き器(玉子巻き鍋)
卵巻きは本物の銅製を使うことをおすすめします。
扱い方は上のフライパンと同様ですが、使っても「洗わないこと」
ペーパータオル等で拭きとるだけでいいです。
※これは卵焼き専用とし、他の料理に使わないようにします


天ぷら鍋
実用性と耐久性で銅鍋に次ぐものを


和食の調理に必要な器具
万能こし器
みそこし、だしこし、そばあげ、卵や野菜をゆでたり多用途に使える


うらごし器
他の道具ではなかなか代用できない道具で、豆腐や茹で野菜を漉すとそれがよく分かります。パン粉をふるったりする用途にも役立ちます。
※本体(枠)と網は別々ですの注意してください


手前板前
ボウル
冷・熱に強く、丈夫なステン製を。
深みがあり実用的なものが使いやすい。

少人数ならこれだけでOK

ラバーゼ ボウル・ざる・プレート4点
ざる
これも実用的で丈夫な物がよい。
手持ちのボウルより一回り小さなものを選ぶといいです。


盆ザル
魚介を乾燥させたり、塩をふっておいたり、野菜を水切りしたり麺を茹でたり、意外とよく使うのが竹製の盆ザル。

バット
揚げ物からあらゆる下拵えまで、網とセットにしたアルミバットが役立つ

すり鉢
できる限り号数(サイズ)の大きなものを選ぶこと。
小さいものは意味がありません。棒も同じです。
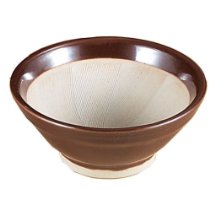
杓子類
鍋からよそう用途だけではなく、計量もできるレードルがオススメ。


木ベラ ターナー
あると非常に便利です

骨抜き
骨抜きの持ち方にはコツがあります。
ハサミ口の方だけを人差し指と親指で締め付けるように持つのです。
そうしないと骨だけ切れたりして、骨抜きの性能を引き出せません。
詳しくは→魚の小骨の抜き方

上に書いた「コツ」などまったく必要のない形態。
実用一点張りというところでしょうか。
初心者には使いやすいと思います。
魚焼き器
様々な種類の焼き器があります。
しかし構造が複雑になりメンテも大変だし、そのわりに効果が疑わしいものばかりで値段もお安くはないようです。
その理由は「矛盾」を解消できないからです。
矛盾とは、煙を派手にあげてアブラを飛ばしながら焼くのが理想なのですが、それを逆に押さえ込む機能を強化しようとしてる事です。
ここは昔ながらの知恵で行くしかないでしょう。
千円もしない二段式の焼き網、これを二つ買うのです。
そして二枚重ね、強火にして焼きます。
他にもまだ必需品として、菜箸・布巾・アク取り&揚げ物の網じゃくし・キッチンばさみ・保存容器・油こし器。オープナー類・ピーラー・おろし金などがありますが、これらは近所の店で容易く入手できますし、性能に大きな差はありません。












